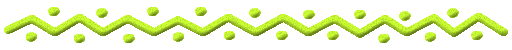 |
真宗用語の基礎知識
|
「仏教用語は難しい」と言われますので、このコーナーでは住職が簡潔に解説いたします。
|
悪人正機(あくにんしょうき) |
| 第1回目は浄土真宗の要(かなめ)の用語でもあります悪人正機です。 悪人正機とは阿弥陀仏の救いのめあては善人でなく悪人であることを表す言葉です。 簡単に言いますと悪人とは「自分の力では悟りを開くことの出来ない者」、反対に善人とは「自分で悟りを開くことが出来るとうぬぼれている者」と私は理解しております。 正機は「めあて」ということです。 悪の自覚の上に浄土真宗の救いが成立し、悪の自覚の上にすべてが「もったいない」「有り難い」と受け止められるのです。 |
阿弥陀如来(あみだにょらい) |
| 「阿弥陀」とは「限りなきハタラキ」という意味のサンスクリット語です。 「如来」とは「如」は「ごとく」であり、我々の思慮分別を交えない「あるがままの世界」という意味。 「来」は「やって来た」ということで、「阿弥陀如来」とは「こうあって欲しい」「ああなって欲しい」という我々の勝手な思いを打ち砕き、すべては縁起の法によって成り立っていることを知らせる「限りなきハタラキ」のことです。 生と死に代表されるように、何事にも善悪をつける我々の分別を打ち砕くハタラキをしてくださるのが阿弥陀如来さまです。 |
易行道(いぎょうどう) |
| 「易行道」とは「難行道(なんぎょうどう)」に対する言葉です。 「難行道」とは悟りを開く(仏になる)ために自力の修行を続ける方法のことで、悟りを開くことが困難であるためこう呼ばれるようになったもの。 反対に「易行道」とは、自力の修行で悟りを開くのでなく、阿弥陀仏の「必ず救う」という誓い(本願)を信受(疑いなく受け入れること)し念仏を申すことによって命終の後に仏になる方法のこと。 「易行」とはやさしい行という意味であるが、本願を疑いなく受け入れることは理論や道理を超えた道であるためむしろこちらの方が現代人には難しい。 |
因果(いんが)縁起(えんぎ) |
| 因果とは物事が起こる原因とその結果を言います。 縁起とは物事の起こる条件を言います。 因果といった場合、因には縁起が含まれており、物事はすべて「因」があり「縁(条件)」がそろって「果」を招く(果が起こる)と仏教は説いております。 地球や人間が誕生したのも、誕生する因があり縁がそろって結果として誕生したのです。 仏教はこのような「因果の道理」あるいは「縁起の法」を根本とした教えですので神のような創造主は認めませんし、物事の原因を方角や日のせいにしないのです。 |
回向(えこう) |
| 回向とはふり向けるということですが、親鸞聖人は阿弥陀如来の救いとして回向という言葉を使用しております。 一般には「追善回向」(亡くなった者は自分の力で善根を積むことが出来ないので、生きている者が亡くなった者のために善を積みその功徳を回してあげる)という意味で回向という言葉が使われております。 親鸞聖人は「私」の救いのために阿弥陀如来が功徳を回向してくれていると受け止め、私たちには功徳を回向する力など一切持たないと認識されました。 このあたりが浄土真宗と他宗派との違いです。 |
往生(おうじょう) |
| 往生とは字の通り「往(い)って生まれる」ことです。 どこへ往くのかというと、それは「お浄土」であり、どう生まれるのかというと、それは「仏」として生まれることです。 人としての「いのち」が終われば、お浄土に仏さまとして生まれるのが私たちの「いのち」のありようであることを仏教は教えてくれます。 私たちは「形」にとらわれて「いのち」を見ようとしませんが、無数の「縁」の集合体である我々の「いのち」は、肉体の死によってその制限から解き放たれ、自由な活動を始めるのです。 「死=往生」でなく、完全自由な故人の活動を感じるとき、往生は成立するのです。 |
観経(かんぎょう) |
| 観経は浄土三部経(略して大経・観経・小経と言う)の一つで、正式には仏説観無量寿経といいます。 「王舎城の悲劇」と呼ばれるアジャセ王子の逆心によって幽閉された母イダイケ夫人の要請によってお釈迦さまが説かれたお説法です。 阿弥陀仏の浄土に生まれるための定善(精神を統一した)13種の観法と、散善(精神を統一しない)の善行と念仏の法を9種類に分けて説かれた経ですが、最後には弟子アナンに念仏一行を付属されたため、親鸞聖人はこの経は隠顕(隠された意味がある)の経とみられ、難しい善行よりも易しい念仏を勧めている経であることを明らかにされました。 |
帰敬式(ききょうしき) |
| 本願寺参拝部の説明では「浄土真宗の門徒として、阿弥陀さまのご尊前(そんぜん)で、み教えに帰依することをあらわす生涯ただ一度の大切な儀式です。 受式後は、これまで以上に門徒としての自覚を深め、本願寺や寺院で行われる法要、諸行事に積極的に参加し、御同朋(おんどうぼう)の社会をめざして歩むことが望まれます。」とあります。 帰敬式は仏教徒としての名のりです。 ご門主やご門主の代理の方からおかみそりを受け、仏教徒としての名(法名)をいただき、阿弥陀さまに仏教徒(門徒)としての生き方を誓う場が帰敬式なのです。 現在は自分で考えた法名を申請することが出来ます。 お寺にご相談ください。 |
苦(く) |
| お釈迦さまは「一切皆苦」(すべてのものは苦である)と示されましたが、この場合の「苦」とは「思い通りにならないこと」を言います。 普通私たちは苦を一つの現象と考えておりますが、お釈迦さまは思い通りにならない人生そのものが苦であり、思い通りにならないものを思い通りに出来ると錯覚するところに生じるのが「欲」であり「怒り」「愚痴」といった煩悩であると説かれております。 思い通りにならない人生を歩んでいることを知らされ、すべてが縁によって成立している大きないのちの世界に気がつくと、欲・怒り・愚痴の存在である自分が嫌になり、真の人間性を探す旅が始まるのです。 |
賢善精進の相(けんぜんしょうじんのそう) |
| 賢く善い行いに励む姿のこと。 親鸞聖人は、虚仮不実(うそ・いつわり)の凡夫でありながら、外面だけを賢者や善人のような「賢善精進」の人のように振る舞うことを厳しく戒められました。 私たちはテレビや新聞などの報道で極悪非道な事件の犯人に対して裁判官でもないのに「これは死刑だ」などと裁いておりますが、その姿こそが賢善精進の相なのです。 「私には人殺しは出来ない」という人がたくさんおりますがはたしてそうでしょうか。今まで人殺しをしなかったのは縁がなかっただけなのです。逆に戦争のような縁があれば何人もの人を殺してしまう私たちです。 自らを誇るのでなく、そのようなご縁がなかったことに感謝しましょう。 |
五逆罪(ごぎゃくざい) |
| 五種類の重罪のこと。 ①殺父 父を殺すこと ②殺母 母を殺すこと ③殺阿羅漢 聖者を殺すこと ④出仏身血 仏の身を傷つけて出血させること ⑤破和合僧 教団の和合を乱し分裂させること 以上の五つを五逆罪と呼ぶが、仏教では「行為」だけでなく「思い」や「言葉」も罪となる。 つまり「父親なんか死んでしまえばいい」と心の中で思ったり、言葉に出しても罪となるのです。 阿弥陀さまは五逆罪を犯した者も救いますが、その救いに甘えることなく、正しく生きることの大切さを御本願で示されました。 |
慚愧(ざんぎ) |
| 罪を恥じること。 「涅槃経」には『慚は人に羞づ、愧は天に羞づ。これを慚愧と名づく。無慚愧は名づけて人とせず、名づけて畜生とす。』とあります。 自分の考えや行為・言動に恥ずかしいという思いを持つのが人間で、恥ずかしさのないものは動物と同じであるとされます。 浄土真宗の信心のカナメとなる言葉がこの「慚愧」という言葉ですが、特に「天に羞づ」という言葉が大切です。 人まえでは行為や言動も善人ぶっておりますが、人が見てなければ何をしでかすか分からない私たちです。「天に羞づ」とは真実に照らし合わせるということでしょう。 もちろん真実は阿弥陀如来のことです。 |
自信教人信(じしんきょうにんしん) |
| 阿弥陀仏の救いを自ら慶び、人にもその救いを伝え共に慶ぶこと。 「自信教人信」の「信」を「信じる」としますと誤解を生じるおそれがありますので、あえて上記のように表現しました。 例えば、私たちが「ネ、見て見て!きれいな夕日だね。」と感動を共有したいと思う心と同じような行動が「自信教人信」という言葉だと思います。 阿弥陀仏の救いを慶ぶ者は、必ずその慶びを人にも伝えたいと思うものです。 その代表が僧侶だと思います。 浄土真宗は世襲制によってお寺が維持され、教えが深みをもって伝えられてきましたが、僧侶や門徒の基本姿勢として「自信教人信」の言葉を大事にしたいものです。 |
親鸞聖人(しんらんしょうにん) |
| 浄土真宗の開祖。1173年~1262年。 9才からの20年間、比叡山において自力の悟りを目指し修行されたが断念。 29才で比叡山を下り、吉水の法然上人のもとで上人から阿弥陀仏(他力)の救いを聞き門弟となる。 35才の時、法然門下をねらった念仏の弾圧によって越後に流罪となる。 4年後赦免となるが、妻の恵信尼さまや子どもと共に関東に移住し、主著の「教行信証」の草稿をまとめたり阿弥陀如来の救いを人々に伝える。 62、3才の頃京都に戻り「教行信証」を完成させ、その他「三帖和讃」や「二門偈」など数々の著作を撰述。 1262年1月16日(新暦)に90才で往生。 |
| このページトップへ |
 今月の記事メニューにもどる |
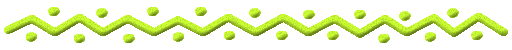 |